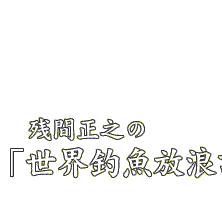作者紹介
残間正之
1953年1月29日、北海道生まれ。フォトジャーナリスト。ファッション、会社案内、カタログなどのコマーシャル写真を撮る一方で、アウトドア&釣り雑誌の企画や撮影、執筆も行う。世界61カ国の秘境に住む民族を訪ねつつフライ・ロッドを振る。著書多数。

|
「世界釣魚放浪記」
(エイ出版/1500円(税別)/2001.10.1発売)
海外の釣り紀行「だからロッドを抱えて旅に出る」の続編!フライだけでなくソルトのルアーも多少含まれています。 |

|
|
ボクが生まれ育ったのは北海道南部、渡島半島の丹羽村。明治の始め、戊辰戦争で敗れた会津藩藩士と農民たちが開墾した開拓村である。
「明治25年3月21日、会津猪苗代地方より移住したる12戸、49人を以て呱々の声を揚げ、往来すべき道路なく、指導を受くべき先住者なく、或いは病気に侵され、群虻群蚊(アブやカの群)に瞥され、或いは猛熊に追われ、或いは屡々洪水に襲われ、衣破れるとも補綴すべき材料なく、冬寒むけれど一枚の夜具もなく、一家族数名は寄り添って炉端に一夜を明かし、其の困難辛苦の状、今日想像を能わざるが如し……」。この地の開拓に心血を注いだ会津藩家老職の直系丹羽五郎が丹羽村建村35年記念祭の式辞の冒頭で述べた開拓当時の様子である。
明治25年といえば、今から100年ちょっと前。当時の後志利別原野は全くの未開地。開拓者たちはアイヌの案内で利別川を遡り、十数キロ上流の目名川の合流地点に最初の一歩を記した。それからクマ笹で屋根を葺いた丸太小屋を建て、空も見えないほどに密集する巨木やクマ笹を切り開いて道をつけ、ヒグマやアブの大群と戦いながら徐々に開墾したという。
開拓者たちは厳寒の中で着のみ着のまま、その日の食べるものはおろか、一粒の種にさえこと欠き、怪我をしても包帯すら無い有り様。マッチはおろかランプすら無く、火打ち石で火を起こし、菜種油の行燈を灯したという。
食料の自給を目指し、馬鈴薯、カボチャ、ソバなどを作付けたが、度々洪水に見舞われ、馬鈴薯だけで冬を越すこともあったという。当時の利別川は密林地帯を蛇行しつつ縦横無尽に流れ、イトウやシャケの宝庫であると同時に、大雨が降る度に氾濫する暴れ川として恐れられていた。実際、ボクの子供のころにも何度か洪水に見舞われ、田畑が水に浸かり、家屋や家畜が流されたのを覚えている。
現在の利別川流域は護岸工事とバイパス化が施され、広大な水田と牧場が広がって当時の苦労の面影をはかり知ることもできない。と同時に、この地で数千年の歴史を刻んだイトウは姿を消し、秋の訪れと実りをもたらすシャケは漁師のヤナで一斉に捕獲され、あわよくヤナを逃れて上流に遡ってもダムで行く手を阻まれ、自然産卵の道は閉ざされてしまった。

夏の夜、鎮守の森を幻想的な光で染めた蛍は過去のものとなり、カエデの樹液に集まった昆虫たちの多くも、農薬の空中散布で姿を消してしまった。庭先を根城にしていた野兎は消え、イタチやムササビ、蝦夷リスなども今では目にすることができない。入植からわずか百年ほどで、数千数万年の歴史を刻んだ自然の多くを失ってしまったのである。人間に豊かな生活をもたらす開発という名目の下で。
ボクが子供のころまでは利別川でも年に数匹のイトウが捕獲され、話題になったものである。最後に見たのは小学4年の時で、湿地を埋め立てている最中に泥の中から捕まえられたもので、見るも無惨に痩せ衰え、頭でっかちのナマズのように見えた記憶がある。
利別川の支流、目名川や真駒内川の上流部はエゾイワナの宝庫であり、その源である狩場山はヒグマの聖地だった。また日本海と太平洋の分水嶺でもある遊楽部岳はヤマメやサクラマス、そして2尺以上もあるエゾイワナの聖地だった。それらを守るのはヒグマでありマムシである。また、東部は奇岩怪石の折なす風光明媚な日本海に望み、海の幸の宝庫でもある。
子供の頃、ボクは家の前を流れる農業用水路でよく遊んだ。幅3メートルほどの用水には、金ブナ、ウグイ、ドジョウ、カジカ、ゴタラッペ、カラス貝、八ツ目ウナギ、赤ハラ、ヤマベ(ヤマメ)、トゲウオ、カヤナギ(体長15センチほどの陸封型?の八つ目ウナギ)などが群れ、遊び相手にこと欠かなかった。
猫柳のつぼみが膨らみ、あたり一面の雪の原から清流が顔を覗かせるとヤマベ釣り、山の雪が解け始めるとエゾイワナ、そして水が温む頃になると、勉強もそっちのけで八ツ目ウナギを狙って夜中まで川面に目を凝らした。夏になるとモリを持って川に潜り、カジカやヤマベを突き、近所の畑から失敬したトウモロコシやジャガイモと共に焚き火で焼き、空腹を満たした。秋になって台風が大水をもたらすと秋アジ(シャケ)もその小川を遡上した。そんな時は早朝から大きなモ
リを持って土手に陣取り、ひたすら獲物を待ち受けた。そして、年に何度かはそんな努力が報われ、両手に抱えきれないほどの秋アジを捕ることができた。
また、近所の池にはコイやフナ、ウグイがたくさんいて、放課後、毎日のように釣り糸を垂れた。
当時、リール竿やナイロンテグスがまだまだ高価で、おまけに1メートルものコイを釣り上げるようなテグスは入手困難だった。そこで、農作業に使う綿糸を4〜5本丹念により合わせて代用にし、裏庭の竹を切って先端に結び付けた。青々とした生の竹は、曲がった時の復元力には欠けるが、どんな大物がかかっても折れることはなかった。畑から堀り出したドバミミズを丸ごと針に引っかけ、水面に放り込む。そして葦の間に潜みコイが食い付くのをじっと持つ。そして、そんな時に限ってヨシキリがギシギシ、ギギ、ギシ、ギシと、まるでコイに危険を知らせるかのようにやかましく啼き叫び、その度にボクはさらに身を低くしてセルロイドの棒ウキが沈むのを待ったものである。
また、この池では冬になるとコイやフナが手掴みできた。カンダハのスキーを履き、片手にブリキのバケツを持ち、氷の張った池の上を夏場に目星を付けておいた倒木まで慎重に行く。そして、氷からわずかに突き出た倒木の周りの一部に穴を開け、そこから手を突っ込み、倒木の下で冬眠しているコイやフナを捕まえる。なにせ熟睡中なので、どんなに水中を引っかき回しても魚は逃げない。それどころか、手の温もりを求めて寄り添ってくる魚もいるくらいだった。
そんなボクも、中学生になると近所の小川や池では物足りず、いっぱしのアングラーを気取って、山奥のイワナを求め歩くようになった。当時の我が家は、水田と酪農を営み、万造さんやカオちゃんという使用人もいた。十数頭の乳牛を世話しつつ、使用人共々、放牧された牛に群がるクマアブを生け捕りにして虫カゴに集めた。そして、休みの日になると、夜明け前に相棒の犬を従え、自転車のペダルを必死に漕いで山奥の沢を目指した。
その沢は熊戻り渓谷と呼ばれ、エゾイワナの宝庫だった。利別川支流の真駒内川の奥のまた奥、狩場山の山懐にあり、長年の浸食で深くえぐられた谷底には、年中大岩を転がすような流れが漲っている。見下ろすと足のすくむような谷の両わきは熊笹に覆われ、熊ですら谷に降りられないことから、熊戻り渓谷と呼ばれるようになったのである。
(続)
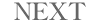
|
|